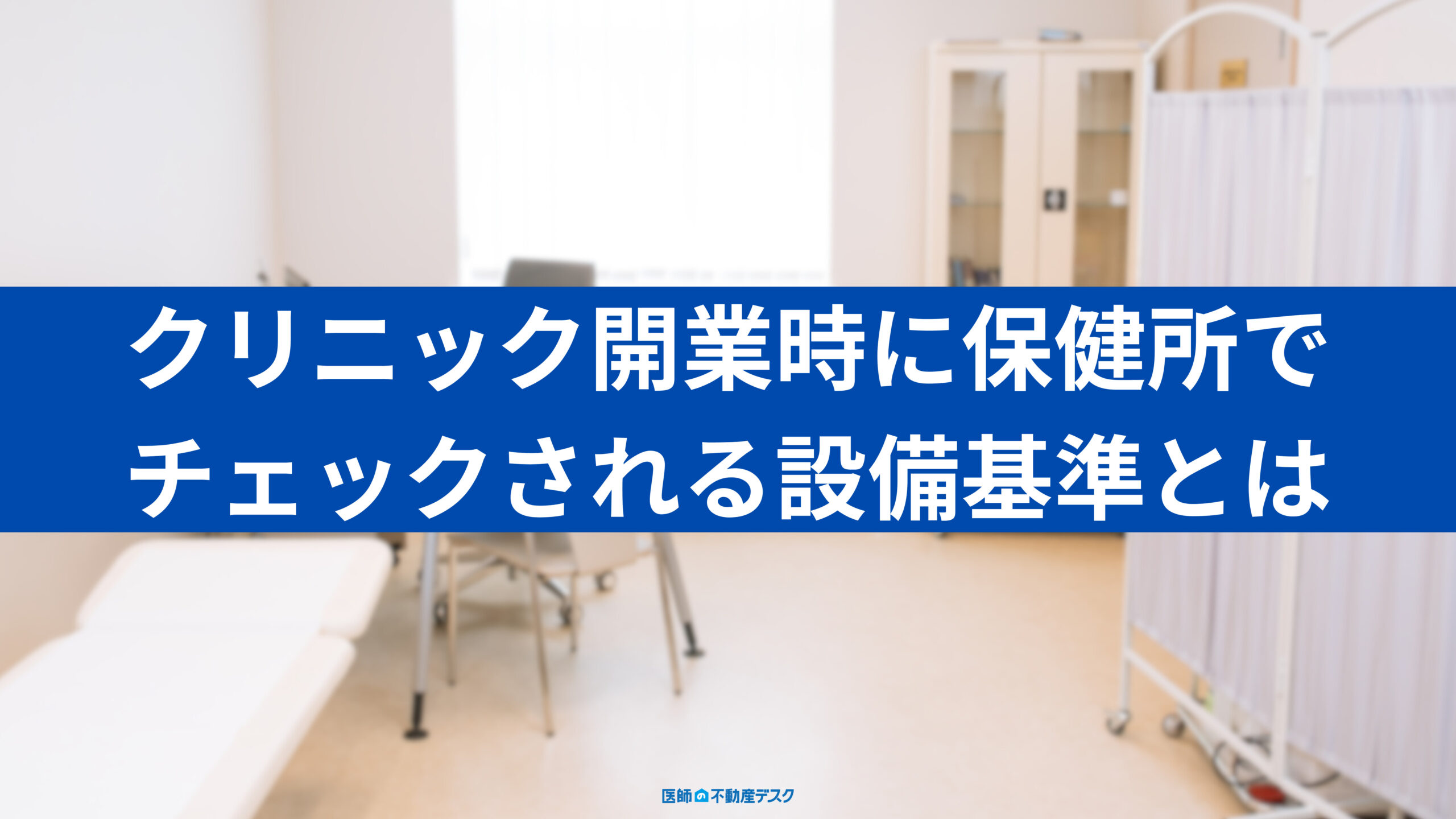「工事完了後に保健所の検査で指摘され、開業が遅れてしまった…」そんなトラブルが起きることがあります。
クリニックを開設する際は、医療法に基づき保健所への開設届出と立入検査が行われ、施設の構造や設備が細かくチェックされます。
この記事では、保健所が確認する具体的な設備基準や注意点を解説します。
ただし、基準や運用は自治体ごとに異なる部分もあるため、必ず開業予定地の保健所へ事前に相談してください。
目次
保健所申請時にチェックされる主なポイント
クリニック開業時に保健所が確認するのは、主に以下の様な施設基準や設備条件です。
9.9㎡以上の診察室
診察室は一般的に9.9㎡(約3坪)以上とされています。
ベッド、医療機器が設置された状態でも安全に診療できる広さが求められます。
また、他の室への通路となるような構造ではなく、明確に区画されている必要があります。
診察室と処置室を兼用する場合は、処置室として使用する部分をカーテンやパーティションで区画することが望ましいとされています。
待合室の設置
診察室と明確に区画することが求められ、3.3㎡(約1坪)以上が標準とされています。
手洗い設備
診療行為の前後に衛生管理を徹底するため、診察室内に手洗い用の流しが必要とされます。
導線の区画
クリニックは、他の施設と機能的かつ物理的に区画されている必要があります。
①商業施設やビルの場合、階段や廊下などの共用部とクリニックが明確に区画されていること。
②事務所が併設されている場合は、それぞれ別の出入口と専用階段が設けられているなど明確に区画されていること。
③居宅が併設されている場合は、それぞれ別の出入口があり、廊下など共有することなく明確に区画されていること。
クリニック開業物件選びで注意すべきこと
物件選びの段階から、前項のような基準に適合できるかどうかを考慮することが重要です。
注意すべきポイント
- 診療室が確保できないほど狭い物件は避ける
- 換気設備が足りているか、場合によっては増設できるか
- 給排水工事が可能かどうか
- 出入口や廊下幅など十分な動線が確保できるか
事前相談の重要性
設備基準は厚生労働省の医療法施行規則に基づいていますが、実際の運用は自治体ごとに若干異なります。移転や分院展開の場合でも、管轄の保健所が異なる場合は注意しましょう。
必ず開業予定地の保健所に図面段階で相談する
工事開始・完了後に設計変更が必要になっては追加コストがかかります。最悪の場合にはクリニックとして開業ができないということも起こり得ます。このような事態に陥らないよう、事前確認・相談をしっかりと行うことが重要です。自治体ごとに「診療所解説案内」などの資料を配布している場合もあるので、確認してみましょう。
まとめ
クリニック開業にあたっては、保健所の確認を前提とした物件選び・内装設計が不可欠です。診療室の広さや手洗い設備などの施設基準をクリアしていないと、開業延期のリスクもあります。特に「工事後にNG」という事態を避けるため、設計前・物件選定時点で、開業予定地の保健所に相談することを強くおすすめします。
医師の不動産デスクでは、物件紹介から内装相談までトータルにサポートしておりますので、クリニック開業をお考えの先生はお気軽にお問い合わせください。
【参照元】
厚生労働省「医療法施行規則」
https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050
東京都保健医療局「診療所・歯科診療所の開設等」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/hokenjyo/minamitama/youshiki/shinryoujotou/shinryoujo-shika
※実際の基準や申請手続きは各自治体によって異なる場合があります。必ず事前に管轄の保健所にご相談ください。